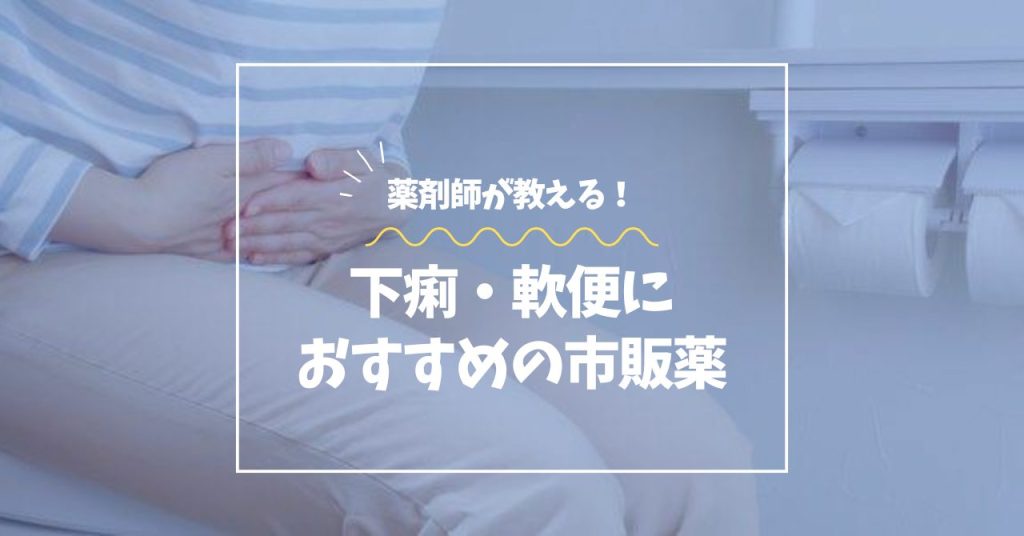管理栄養士が解説!つらい便秘の解消法について食べ物や運動、薬と予防法をご紹介

「忙しくてトイレが後回しになっているな……。」「最近、お腹が張ってすっきりしない……。」そう感じることはありませんか?便秘は放置すると、生活の質を低下させ、他の不調を招いてしまうことも。
このコラムでは、便秘の定義から原因、解消するための方法や予防法をご紹介します。


大学卒業後、介護食品メーカーで営業を2年間従事。その後、管理栄養士に。料理動画撮影やレシピ開発、商品開発、ダイエットアプリの監修、栄養価計算などの経験あり。 現在は、記事執筆・監修、特定保健指導をメインに活動中。
便秘とは?

「数日便が出ていない……便秘かな?」と思っている方もいるのではないでしょうか。まずは、医学的に便秘とはどのような状態を指すのか、定義や種類を理解しましょう。
便秘の定義
医学的な「便秘」とは、単に便が出る回数が少ないことだけを指しているのではありません。
便通異常症診療ガイドライン2023では、「本来排泄すべき糞便が大腸内に滞ることによる兎糞状便・硬便、排便回数の減少や、糞便を快適に排泄できないことによる過度な怒責、残便感、直腸肛門の閉塞感、排便困難感を認める状態」と定義されています。
つまり、以下の症状に心当たりがあれば、それは便秘のサインです。
- 排便の頻度が少ない
- 便が硬くて出にくい
- 便を出すときに過度な力みが必要
- 出してもすっきりしない状態
毎日出ていても、スッキリしないという方も便秘の可能性があります。回数だけではなく、「快適に出せているか」がポイントです。
あなたの便秘はどのタイプ?原因を知ろう

便秘は、原因によるものと症状によるものの2つに分類する方法があります。
原因による分類では、一次性と二次性に分けられます。
一次性便秘症
主に腸の機能異常のものを指しており、生活習慣やストレスなどが原因で起こるものを指しています。
二次性便秘症
他の病気や薬剤の影響で起こる便秘です。一次性便秘とは異なり、原因となる病気や薬を特定して、それらに対応することが重要だといわれています。
症状による分類では、便が出ない「排便回数減少型」と便が出せない「排便困難型」に分けられます。また、この2つは合併することもあります。自分の便秘のタイプを知っておくことで、対策を立てるヒントにもなりますよ。
なぜ便秘になってしまうのか?
便秘の原因は一つではなく、食生活や生活習慣、基礎疾患などさまざまな要因が関わっています。ここでは、原因となりえるものを一つずつ解説していきます。
食生活の乱れ
食生活の乱れは、便秘の原因になることがあります。忙しくて食事を抜いてしまったり、栄養が偏った食事をとりつづけたりすると、食物繊維や水分の量が不足し、便秘につながることがあります。
また、偏った食事を続けると腸内環境が乱れることもあり、便秘の原因になるのではないかといわれています。
運動不足
運動不足も、便秘を招く要因の一つです。運動不足になると、腸の蠕動運動が低下してしまい、便を外に出す力が弱くなります。
また、腹筋や骨盤底筋など排便に必要な筋力が落ちると、便を押し出す力が弱くなり、便秘になりやすいといわれています。日常的に運動する習慣がない方や、デスクワーク中心で体を動かす時間が少ない方は要注意です。
生活習慣やストレス
食生活や運動以外の生活習慣や、環境要因も便秘に影響するものがあります。
例えば、ストレスによる自律神経の乱れは、腸の働きを低下させます。副交感神経は、腸の蠕動運動を活発にすることで排便を促しますが、ストレスなどで交感神経が優位になると、腸の動きが鈍くなり、便秘につながります。
また、仕事などで忙しくなかなかトイレに行けない環境だと、便意を我慢する習慣がつきます。排便を我慢することが続くと、便意そのものが感じにくくなってしまうケースもあるようです。
その他に考えられる要因
ここまで説明した生活背景の要因以外だと、体の病気や薬剤の影響で起こる便秘もあります。
例えば、大腸ポリープや大腸がんなど腸管が物理的に狭くなる病気や、潰瘍性大腸炎やクローン病など、腸の内容物を送るのが滞り便秘の症状が出ることがあります。
それ以外にも内分泌系の病気や神経疾患など、さまざまな病気が便秘に関与していることがわかっています。薬剤の中でも、副作用として便秘が起こりやすくなるものもあります。
また、女性の場合は、ホルモンバランスの変化により、便秘になりやすいことがあります。特に妊娠中は黄体ホルモンの影響により腸の働きが抑制されたり、子宮の圧迫などによって便秘につながりやすいです。
便秘を解消するには

実際、便秘になってしまったら、どう対策するのがよいのでしょうか?ここでは食事や生活習慣で日々の生活に取り入れられるポイントをいくつかご紹介します。
食物繊維・オリゴ糖
食物繊維は、排便をスムーズにする働きのある栄養素です。食物繊維には2種類あり、水に溶ける水溶性食物繊維と、水に溶けない不溶性食物繊維があります。
水溶性食物繊維は野菜や海藻、果物に、不溶性食物繊維は穀類や豆類に多く含まれています。どちらも両方バランスよく食べましょう。
また、オリゴ糖と呼ばれるものの中には消化されにくい「難消化性オリゴ糖」も食物繊維に分類されます。その中でも「フラクトオリゴ糖」は、そのまま大腸に届き腸内環境を改善してくれる働きがあり、便秘の解消にも効果が期待できます。バナナや玉ねぎに含まれていたり、特定保健用食品の中にも含まれているものがあります。ただし、とりすぎると便がゆるくなることもあるので、注意しましょう。
発酵食品を取り入れる

便秘を解消するのに、発酵食品を取り入れるのも有効だといわれています。発酵食品には、乳酸菌やビフィズス菌など生きた微生物「プロバイオティクス」が含まれており、継続的に摂取することが必要です。食品としては、ヨーグルトや納豆、キムチなどが該当します。
一方、前述でご紹介した食物繊維やオリゴ糖は、善玉菌のえさとなる食品で「プレバイオティクス」と呼ばれています。プロバイオティクスとプレバイオティクスを含む食事は便秘改善に有効なのではないかといわれています。
水分を意識する

適度な水分摂取は、便秘解消につながるという報告があります。コップ1杯の水や牛乳を飲むと、胃腸の働きが活発になり、排便が促されるといわれています。水をとる習慣がない方は、まずは起きたらコップ1杯の水分をとることから始めてみましょう。
ただし、水分だけではなく、食事からしっかり食物繊維をとることが前提です。
適度な運動

適度な運動は、腸の動きを促し、便秘解消にもつながる可能性があります。実際、ジョギングやウォーキングなどの有酸素運動は便秘の症状改善に効果があるという報告がされています。忙しい日々の中でまとまった運動時間を確保するのが難しい場合は、今の生活活動の中に運動を取り入れることをおすすめします。例えば、通勤で駅を使うのであればなるべく階段を使うようにしたり、テレビCMの間だけでもその場で足踏みをしたりすると、運動する時間を確保することができます。
また、骨盤底筋や腹筋、背筋を鍛えることでも便秘の改善につながります。
薬を上手に使う

生活習慣の改善に取り組んでも、便秘がなかなか解消しない場合は薬に頼るのも選択肢の一つです。
便秘の治療薬にはさまざまな種類があります。例えば、酸化マグネシウムなどの浸透圧性下剤は、腸内の水分量を増やして便を柔らかくしてくれます。膨張性下剤は、水分を含んで膨らむことで便のかさを増やしてくれます。この2種類は、自然に近い排便を促すため、初めて薬を飲む方にもおすすめです。
刺激性下剤は、大腸に直接働きかけ排便を促しますが、耐性がついてしまうことがあるため、一時的に使う程度にとどめ、使用し続けないように注意が必要です。
どの薬を飲むか選ぶ際は、かかりつけ医や薬剤師に事前に相談しましょう。
便秘を予防するには

便秘は、日頃から予防する生活習慣を身につけておくことも大切です。慢性的に便秘になりやすい方や、生活が乱れがちな方は、以下のポイントを意識してみましょう。
腸内環境を整える
腸内環境を整えることは、便秘の予防にとても重要です。
大腸には約100兆個以上の腸内細菌が存在しており、この環境を良好に保つことが大切です。
腸内環境は、善玉菌・悪玉菌・日和見菌の3種類に分類されています。理想的なバランスは、善玉菌が2割、悪玉菌が1割、日和見菌が7割といわれていますが、悪玉菌が増えると、便秘や下痢といった症状が出てくるといわれています。
腸内環境を整えるには、発酵食品をとりいれることや、善玉菌のエサとなる食品をとることを意識しましょう。
生活習慣を整える
規則正しい生活習慣を送ることは、便秘予防につながります。
人間の腸の動きには、自律神経と体内時計が関わっています。そのため、不規則な生活は、腸のリズムを乱すことにつながります。毎日同じ時間に起床・就寝し、1日3食決まった時間に食事をしましょう。同じ時間に食事をすることで、腸の蠕動運動の効率が上がります。
また、便意を我慢しないことも大切です。前述した通り、便意の我慢は便秘の悪化にもつながります。便意を感じたらできるだけ早めにトイレに行くようにしましょう。
便意の有無に限らず、朝食後にトイレに行き、排便の習慣を身につけるのもよいですね。
適度な運動やストレス発散などで、腸の働きを活発にすることも意識しましょう。
定期的に便をチェックする
日頃から便の状態を観察しておくことも大切です。便は健康のバロメーターともいわれており、色や形状から自分の状態を確認することができます。
理想的なのは、熟したバナナ位の形と柔らかさだといわれています。便秘が気になる方は、自分の便の形状や硬さを「ブリストル便形状スケール」というものでチェックしてみてください。
まとめ

便秘は慢性化すると、日常生活に支障をきたすことがあります。「便秘かも?」と感じたら、早めに対策をしておくことが大切です。便秘の基本は、規則正しい生活、適度な運動、バランスのよい食事です。日々の小さな積み重ねが、便秘の解消や予防にもつながります。どうしても辛い場合は、放置せずにかかりつけ医に相談してみてくださいね。
毎日を快適に過ごすために、すっきりとしたお通じを目指しましょう。
<参考文献>
- 厚生労働省 健康日本21アクション支援システム「食物繊維の必要性と健康」
- 日本消化管学会 便秘異常症診療ガイドライン2023ー慢性便秘症
- 飯田薫子、寺本あい「一生役立つ きちんとわかる栄養学」西東社(2019)