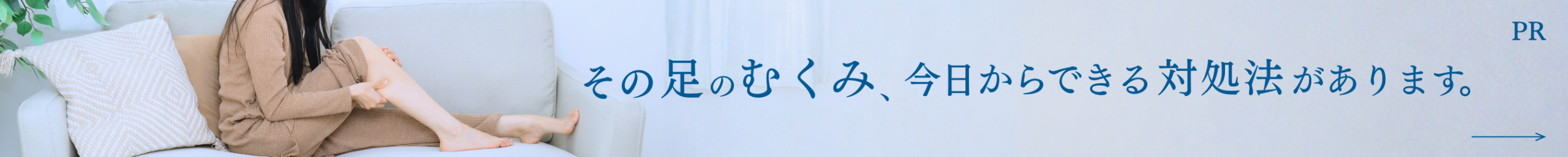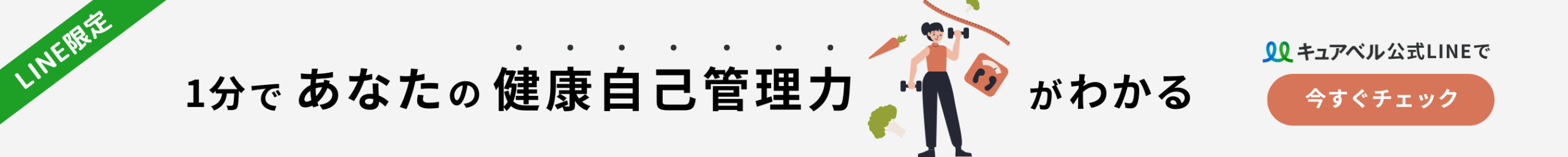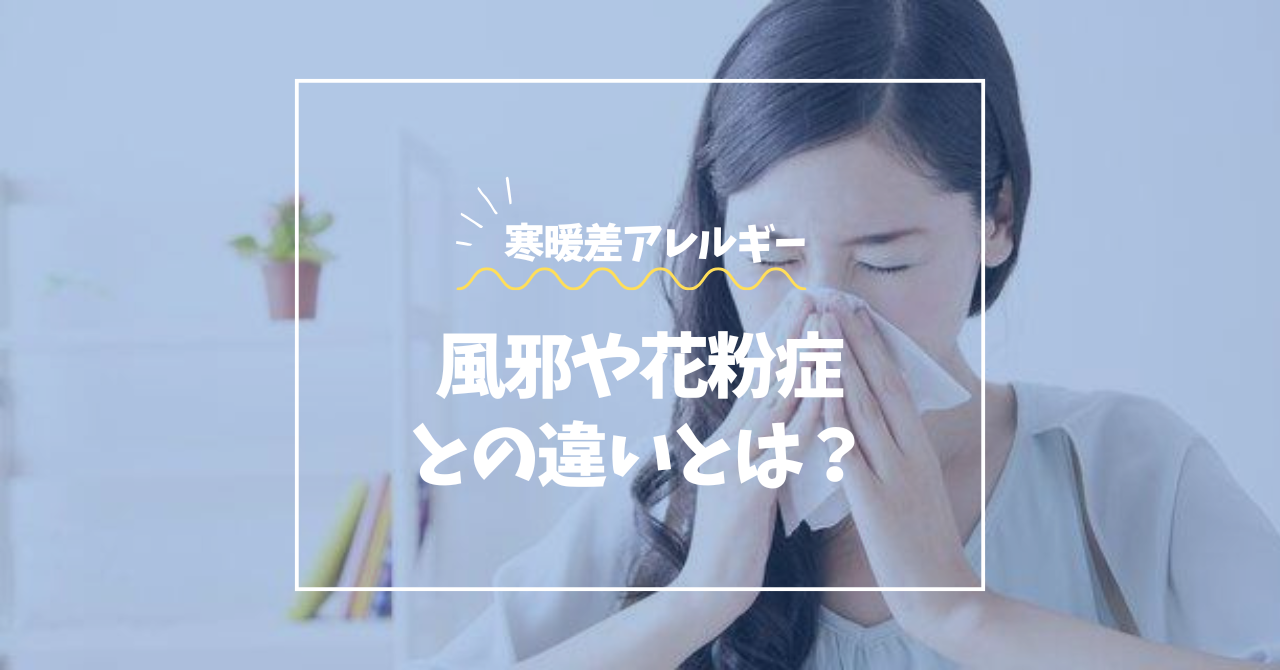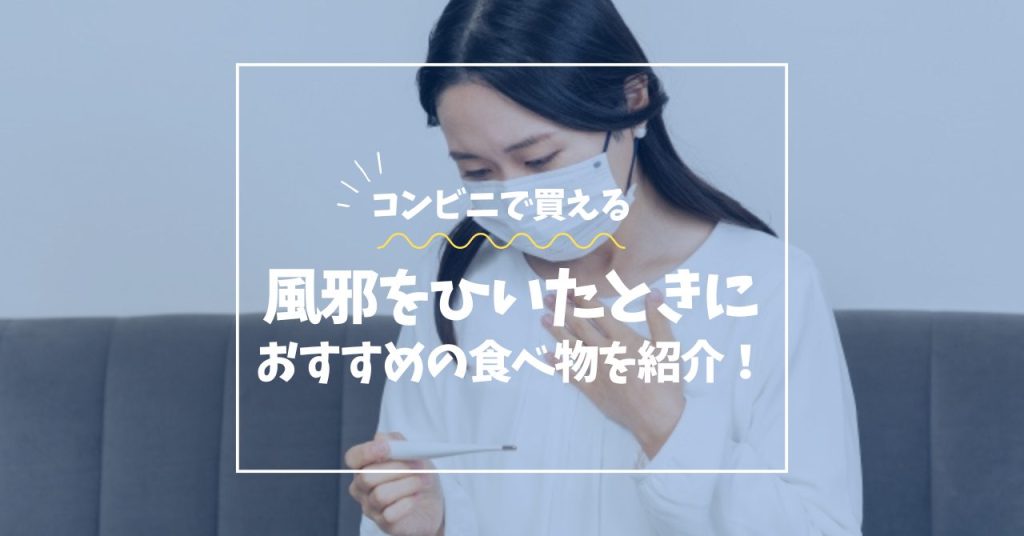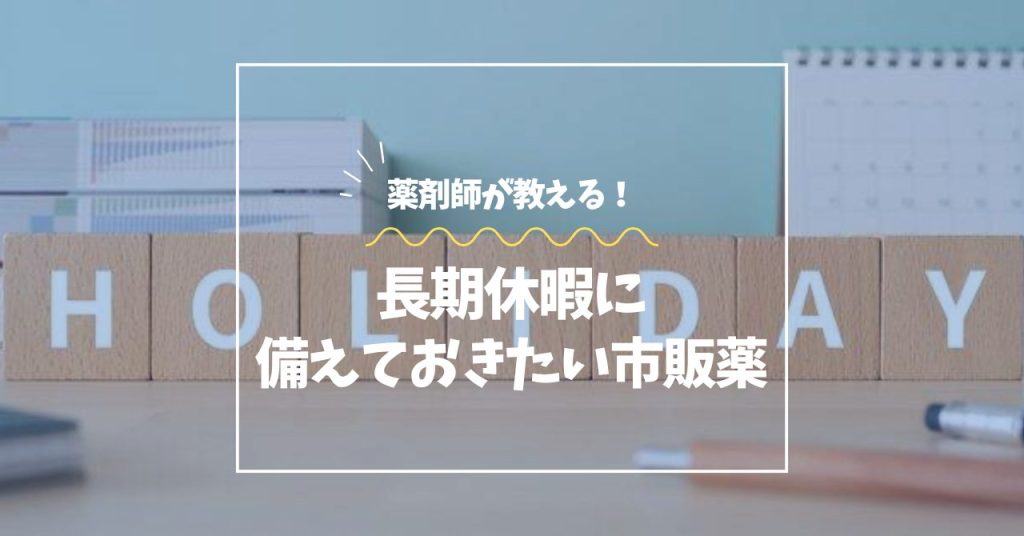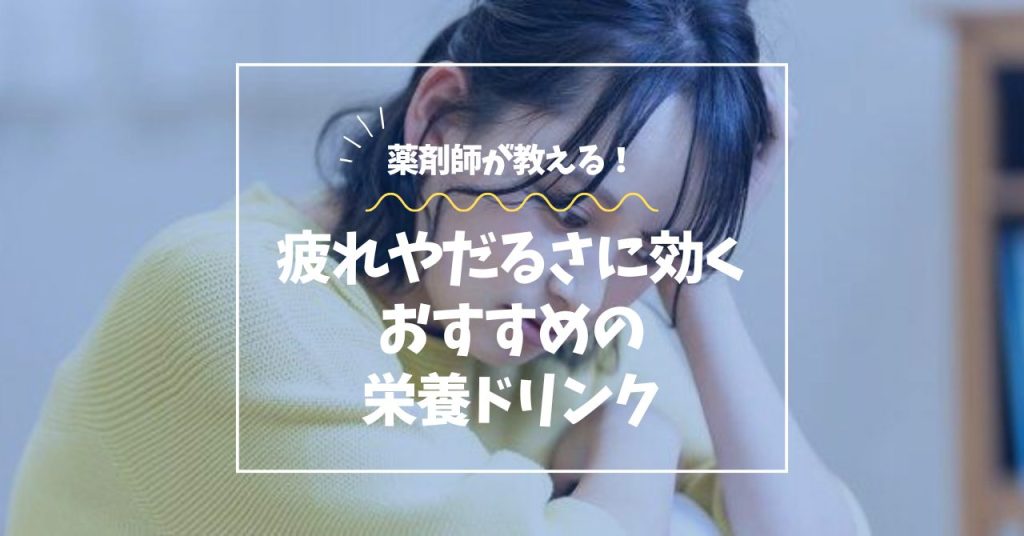冷えが健康に与える影響とは?不調の原因と改善の基本

手足が冷えて眠れない、肩こりや体のだるさが取れない ― そんなお悩みの背景には“冷え”が関係しているかもしれません。冷えは単なる不快感ではなく、血流のめぐりの乱れや自律神経の乱れ、ホルモンバランスの不調など、身体全体に影響を及ぼす可能性があります。
特に女性は冷えを感じやすい方が多く、足先や手の冷え、腰痛、不眠などの症状が出やすい傾向があります。放置すると体調のバランスを崩しやすくなるため、早めの改善と対策が大切です。本記事では、冷えの原因や症状のタイプ、そして日常生活でできる基本的な改善方法を、専門家の視点からわかりやすく解説します。


大学卒業後、福祉施設での栄養管理、企業向けの商品開発、特定保健指導、健康経営支援など多岐にわたる現場を経験。その後、独立し、現在は離乳食教室の運営や米粉パン事業をはじめ、健康をテーマにした複数のプロジェクトを展開中。ライフステージに寄り添った実践的な栄養支援を軸に、食の専門家として「より良い暮らしと健康」を支える活動を続けている。
冷えとは?

「冷え」とは、身体がうまく体温を維持できずに低下するなどして、手足の末端や下半身が冷たく感じられる状態のことを指します。西洋医学では冷え性が診療の対象とならないこともありますが、漢方医学では重要な体調サインとして扱われます。その背景には、自律神経の働きや血のめぐりなど、体温の調整に関わるさまざまな要因が関係していると考えられます。
寒さを感じると脳の視床下部が血管を収縮させ、熱の放散を抑えます。しかし、この仕組みが乱れると慢性的な冷えなどが起こりやすくなります。日本人女性の約7〜8割が冷え性を自覚しており、特に筋肉量の少なさや生活リズムの乱れ、栄養バランスの偏りなどが原因の一つと考えられています。また冷えは女性ホルモンのバランスや月経周期とも関係しているといわれています。
こうした冷えを放置したりせず、日常生活で取り入れやすい冷えの改善と対策を意識することが大切です。身体を温める食品を意識して摂る、下半身を冷やさない衣類選びをする、ぬるめの湯船にゆっくり浸かる、ストレッチや軽い運動を行うなど、ケアを続けていくことが冷えの改善につながるといえるでしょう。
冷えが健康に与える主な影響

冷えは、身体のさまざまな機能に影響を与える要因のひとつといわれています。血のめぐりが滞ったり、自律神経のバランスが乱れたりすることで、体調の変化を感じやすくなることも。特に女性は冷えを感じやすく、放置すると疲労感につながったり、ホルモンのバランスの乱れることにつながります。ここでは、冷えがもたらす代表的な5つの悪影響について詳しく解説します。
免疫力低下と感染症リスク
体温が1℃下がると、免疫力はおよそ30%低下するといわれています。体が冷えると血のめぐりも滞りやすく、体調を崩しやすくなることも。
特に寒い季節やエアコンによる冷えが続く暑い季節は、体を温める工夫を意識するとよいでしょう。適度な運動やバランスの取れた食事、ぬるめの湯船での入浴が、免疫力維持をサポートすることにつながると考えられます。
消化器系への悪影響
腸は“第二の脳”とも呼ばれ、全身の健康や免疫機能にも関与します。内臓が冷えると血流が滞り、免疫機能が低下することがあります。その結果、肩こり・頭痛・不眠・食欲不振などの不調につながるほか、風邪や感染症にかかりやすくなるリスクが高まるのです。
さらに、消化器の働きが鈍ると胃もたれ・便秘・下痢を起こりやすくなります。これによりエネルギー不足や栄養不足を招いて、慢性的な疲労や肌荒れにつながることもあります。
自律神経の乱れ
冷え性と自律神経は深く結びついています。自律神経のバランスが崩れると、交感神経が優位になり、末梢の血管が収縮して手足の冷えを感じやすくなります。また、不規則な生活や睡眠不足、精神的な不安といった要因も自律神経の乱れに影響すると考えられています。冷えを感じやすくなるだけでなく日常生活にさまざまな不調に影響するおそれも。
肩こり・腰痛・関節痛
血行不良により筋肉が固くなると、肩こりや腰のこわばり、関節まわりに違和感を感じやすくなります。特にデスクワークや家事で長時間同じ姿勢をとる方や運動不足になっている方はストレッチなどで身体を動かす習慣をつけると、血行をサポートして身体のこわばりをやわらげることにつながります。
女性特有の不調(生理痛・不妊など)
冷えは女性の健康に大きく関わる要因のひとつ。子宮や卵巣などの骨盤内臓器は血行の影響を受けやすいです。その結果、身体が冷えて下腹部まわりの血のめぐりが滞ることがあり、月経前の情緒不安定、生理中の不快感などを感じやすくなることも。また、卵巣機能の低下や女性ホルモンバランスの乱れ、不妊の原因を招く可能性があるので気をつけましょう。
冷えの原因
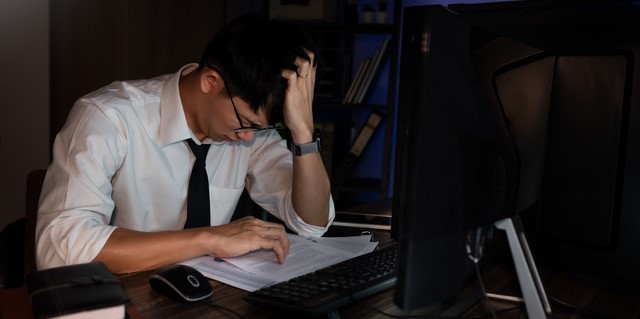
冷えの原因はひとつではなく、いくつかの要素が複雑に関係していると考えられます。例えば、運動不足や偏った食事が続いたり、生活の乱れやストレスフルな環境にいる時間が多かったりすると、環境的な要因で冷えを感じやすくなることがあります。
体質的に冷え性になりやすい方もいますので、冷える要因を見分けることも大切です。
冷えの原因になる要素
- 環境的な要因:季節の変わり目、冷房の効きすぎ、薄着、冷たい飲み物の飲み過ぎ
- 生活習慣の影響:運動不足による筋肉不足、偏った食生活やダイエットによる栄養不足、喫煙習慣など
- 精神的ストレス:自律神経の乱れによる、体温調整機能への影響
- 体質的な要因:更年期などホルモンバランスの乱れ、筋力の低下
放置するとどうなる?将来的なリスク
「冷えはただの不快感」と思い、そのままにしてしまう方も少なくありません。しかし、慢性的な冷えは血流や自律神経のバランスに影響を及ぼし、体調の乱れを感じやすくなることがあります。
冷えは身体のあらゆる機能と関係しており、放置することで思わぬ健康トラブルにつながる場合も。身体の冷えは万病のもとといってもおかしくありません。万が一、冷えによって不調が長続きする場合や症状が改善しない場合は専門医に相談することが大切です。
冷えによって起きる健康リスク
- 免疫力の低下:身体が冷えると免疫細胞の働きへの影響することがある
- 身体の不調:血行不良により老廃物が溜まりやすくなり、腰痛、肩こり、筋肉や関節の痛みを感じやすくなる
- 消化器系の不調:内臓が冷えることで胃腸の働きが鈍くなり、食欲不振や下痢を起こしやすくなる。内臓機能が低下すると生活習慣病のリスクが高まる
- 美容への影響:新陳代謝が滞り、肌の乾燥、くすみ、肥満などにつながるほか、抜け毛、白髪の原因のひとつにも
- 女性特有の不調:ホルモンのバランスが崩れ、生理不順や体調の変動を感じやすくなる
- 精神面への影響:ストレスや冷えによる自律神経の乱れから、意欲の低下、イライラ、気分の落ち込みにつながることがある
冷え対策の基本

冷え性を改善するには、日頃の生活習慣の見直しも不可欠です。改善には「身体を温める力(代謝)」を高める習慣作りが欠かせません。日々の暮らしの中でできるな基本的な対策を紹介します。
冷え改善の基本的な対策
- ウォーキングやストレッチなどの適度な運動
- 食事に根菜(大根、かぼちゃ、ニンジンなど)、イモ類(サツマイモなど)、卵、発酵食品(味噌、チーズ)や、
ショウガ、ネギなど体を温める食材を取り入れる - ぬるめ(38~40℃)のお湯に10分〜15分浸かる入浴習慣
- 羽織もの(カーディガンなど)や重ね着で保温
- 締め付けない服装を心がける
- 3つの首(手首・足首・首)やお腹を保温する冷え性改善グッズ(レッグウォーマーや腹巻)の活用
セルフメディケーションで自身の健康管理を!
もっと手軽に健康情報を受け取りたい方は、キュアベルの公式LINEを友だち追加!週1回の健康ネタ配信・市販薬やサプリメントの検索/比較がLINEでできて便利。今すぐQRを読み取って登録!!
LINEお友達登録でできること
- 毎週届く「季節の健康ネタ」や「今すぐ使えるお薬Q&A」
- みんなが見ている注目コラムから、いま必要な健康情報を入手
- 自分の症状や悩みに合った市販薬やサプリメントの検索・比較・選定をサポート
まとめ
冷えは、免疫力低下や自律神経の乱れ、内臓機能の低下など、全身の不調を引き起こす深刻な問題です。「冷えているかも」と思ったら早めに生活習慣を見直し、身体を温める習慣を取り入れることが健康維持の第一歩です。日々のケアを積み重ねて、少しずつ身体を整えていきましょう。
-
- <参考文献>